<参考20> 京浜運河構想から内湾漁業の終焉へ
(以下の内容は大半が「大田区史」からの引用に基ずく。但し端折って記載しているので原文のままでない箇所が多い。なお一部は引用外で注記として勝手に書き加えた部分になっている。)
条件に恵まれて早くから国際港として発展してきた横浜港に対し、東京港にも大型の船舶が入れるようにしたいという願望は明治の時代から東京の経済界にあったが、横浜から品川までの沿岸は遠浅で航路の開削が必要となるため、資金面の理由により実現には至らなかった。しかし神奈川県側では、浅野総一郎が提唱した臨海工業地帯を建設すべく、大正12年(1913)に京浜運河(株)により京浜運河の開削、埋立地の造成が着手され、これに呼応するように日本鋼管による臨海埋立地への進出が始まっていた。
大正12年(1923)関東大震災により、東京の陸上運輸が壊滅的な打撃を受けた際、内外からの援助物資を積んだ2000トン級の船舶が東京港に進入し、満潮を利用して冒険的な荷役を決行した。このことが停滞を一気に打開する契機となり、内務省港湾調査会は昭和2年(1927)、京浜運河の開削と埋立地造成計画を決定した。
昭和2年は金融恐慌の年で、工事費用が国家予算から支弁される可能性が無かったため、内大臣鈴木喜三郎は、運河の通過料を徴収しない代わりに、埋立地を京浜運河(株)に交付する(但し道路、荷揚場の敷地は都県に寄付させる)条件で、同社に経営を委ねる方針を採った。
当時は第一次世界大戦後の大恐慌のさ中、日本はその解決を中国侵略に求めていった時期である。計画は1万トン級の船舶が航行できる運河を開削し、掘った土砂によって内側を埋立てて工業用地を造成し、臨海工業地帯を開発して生産力増強を図ることを目的とした。また石油・石炭等の直接荷役貯蔵を可能にすることは、有事の際の国防にも資するものと位置付けられた。
具体的には、東京港から多摩川河口先を通って鶴見川河口に至る22.6kmに、水深9m,東京側で幅700m,川崎側で幅600mの汽船航路を開削し、運河を開削した土砂によって630万坪(2000ha)の埋立地を造成するとした。内側埋立地内には延長11km幅200mの艀船(はしけ)航路と、幅100〜150m程度の小運河を設けて水運の便を図り、汽船航路には全線に防波堤を築造することなども計画に記載された。
(この計画による汽船航路は現羽田空港のターミナルビルの辺りを通っているので、この計画が予定通り実行されていれば、羽田空港の現状のような拡張は行う余地が無かった可能性が強い。)
昭和3年(1928)1月末、東京府知事は京浜運河(株)からの出願を受けて、羽田、大森、入新井、大井の4町に対し、計画への賛否を諮った。運河・埋立計画により、地先海面の大半が失われることが、初めて漁民の側に知らされたわけである。これに対して、大森が町ぐるみで反対、羽田町議会も反対を決め、入新井・大井は、埋立地の一部を無償で払下げてくれるなら、という条件つきで承認する旨を回答した。
漁場の喪失は、海苔養殖場、貝類養殖場に止まらず、地先漁業の専用漁業権もその7割を失うというもので、品川から大師に至る6町の漁業従事者2万世帯10万人は、これを生死に関わる問題と受止め、以後大森、羽田、糀谷の3漁業組合が中心となり、5000人規模の反対行動が繰返されることになる。民政党の代議士高木正年の斡旋により帝国議会に対する請願も行われ、漁場埋築を許可すれば、容易ならざる社会問題を引起すばかりでなく、京浜運河がもたらす費用節減効果(年額700万円)を遥かに上回る、年額1800万円の莫大な漁業損失が生まれるとして、政府が埋立事業を免許しないようにとの請願書が提出された。
昭和3年6月、大森漁業組合の役員を父にもち、海苔養殖を生業としていた鳴島音松が、陛下の御助けを願い度い旨の上奏文を懐に、赤坂離宮正門から走り込むという天皇直訴事件が起きる。この直訴事件に衝撃を受けた政府と東京府は、計画の実行について慎重を期さざるを得なくなり、以後7年間の空白期間を迎えることになった。
神奈川県側では京浜運河(株)が、昭和3年(1928)までに鶴見区に隣接する白石・大川町及び扇町の埋立を既に完工していたが、東京側が反対運動により頓挫している間にも着々と工事を進め、昭和11年には計画の大半にあたる830haを埋立造成し、その内630haには工場が建設されて、臨海工業地帯が出来つつあった。
中国侵略の進行に従い、工業生産力増強という国家的な至上命題から、運河開削と用地埋立の実現に迫られた東京府は、工事を民間委託でなく、府の直営で実施することを決断し、昭和10年(1935)府会に事業実施を諮問した。府会では専ら漁業補償について議論され、昭和11年に付帯条項付で工事を承認する案が可決され、東京市会からも同様の答申が行われた。
大森漁業組合などは、再び強力な反対を推し進めようとしたが、時局がそれを許さなかった。日華事変が激しさを加え、軍国主義が謳歌されるという時勢で、国家権力が絶対的であっただけに、強力な反対運動は差控えなければならなかった。絶対反対を押通そうとする闘争から、漁業補償と漁場の換え地を求める条件闘争に切替えざるを得なかったのである。(内大臣高橋是清は恐慌突破のために積極財政政策を採ったが、その多くが軍需産業に向けられたため、軍備の拡大により台頭した軍はシビリアンコントロールを失ったモンスターとなり、1936年緊縮に舵を切った高橋是清はこの年二・ニ六事件によって暗殺されてしまうという状況だった。)
東京府は昭和12年度から補償調査を始めると共に、測量・地質調査など施工の準備に取り掛かった。本工事の実施設計は、大森区の森が崎沖を基点に、北側の品川区鮫洲(さめず)沖までの第一期と、南側の羽田沖までの第二期に区分され、第一期分は昭和18年度までの6年間で完成させるということになっていた。
東京府は補償審査委員会を設置して関係組合と折衝を重ね、それまで交渉が難航していた大森漁協が昭和14年1月に同意書を提出し、第一期工事に関係する全ての漁業者の同意が調った。(翌15年には第二期工事関係の漁協、漁業権者の同意が成っている。)
府知事と関係漁協との間で協定が結ばれ、総額550万円の補償金が支払われたが、その62%が大森漁協に対するもので、これに羽田浦・糀谷浦を合わせた分が全補償額の86%に達する比重を占めた。この数字は当時大田区域でいかに漁業が盛んであったかを示している。
日中戦争は泥沼化し、昭和16年12月には太平洋戦争に突入、東京港はその直前の5月に開港したが、京浜運河の開削は、労働力不足と資材統制によって、18年3月末第一期工事の途中で打ち切りとなった。(工事は、先ず元から海に突出す形になっていた品川猟師町を基点に、南側の南品川宿の沖合いを埋め、その幅で鮫洲沖まで陸続きで埋立てた。次いで立会川河口一帯の海岸に現在勝島運河と呼ばれる水路を開削し、沖に勝島を計画の半分程度埋立てた。(勝島の南側は後に大井競馬場が出来た所で、今では勝島運河の南半分は埋められて鈴ヶ森と陸続きになり、旧運河上に品川水族館が出来ている。) 勝島より南側については殆ど進んでおらず、勝島運河の延長を開削し、平和島の陸側の一部を埋めたあたりで工事は中止されたという。)
結果的に豊かな漁場は破壊され、運河も実現されることは無く終戦を迎えるのである。 (神奈川県側の臨海工業地帯造成計画は、昭和12年に着工され情勢が窮迫した20年秋に打ち切りとなっている。)
戦前の京浜運河の開削は、埋立によって工場用地を造成するという目的をもって行われた。敗戦によって喫緊の目的は失われ、工事は中止されたままになったが、東京府には依然として埋立の権利は残った。
終戦時東京港の港湾施設は国力の疲弊により麻痺状態になっていたが、国が石炭増産政策を打出し、豊洲埠頭や晴海埠頭の建設など、港湾の復興と近代化を求めてきたことを受け、東京都は昭和26年に東京港港湾計画を策定し、従来までの艀船(はしけ)による京浜間の二次輸送態勢を、大型船による東京港直接入港に切替えるべく、港湾の整備拡張に向け再び動き出すことになった。
戦後昭和24年末に制定された漁業法により、当該海域には、海苔養殖や貝類採取のための区画漁業権、定着性の水産生物を対象とした漁業権、特定の網漁法によって漁業を営む共同漁業権などが設定されていた。一方翌昭和25年5月に制定された港湾法では、これら漁業権の対象となっている海域のほとんどの部分を、港湾機能を確保すべき区域に定めたのである。港湾機能の拡充を図ることが、水産資源の確保と相容れない問題を次々に引起すことになったのは当然の結果といえる。
最初の紛争は浚渫土砂の不法投棄問題として発生した。昭和33年に東京都漁協連合会と東京都港湾局は、協議により土砂捨場を設定し、小型の土砂運搬船は品川区勝島町沖(大井埠頭埋立地裏)に土砂を投棄するように申合せていたが、一部の運搬船が指定区域外に投棄を行っていることが発覚し、投棄された土砂にはヘドロもあり、漁場に極めて悪影響を与えるとして、大森漁協は港湾局に抗議した。 (この時問題にされた場所は「上総澪」といわれ、その詳細は分からないが、晴海・豊洲・芝浦近辺で浚渫した土砂を勝島まで持ってこずに、今の有明と台場の間辺りで捨てていたものか。)
昭和34年1月の懇談会に於いて、大森漁協は都港湾局に対し、勝島町沖土砂捨場の場外投棄について抗議するとともに、京浜二区の埋立を前提とした平和島の受電所建設や、大井埠頭の埋立の不法性にも初めて抗議を行っている。
不法投棄が改まらない状況に業を煮やした大森漁協は、同年2月海上ピケを張るなどの実力行使に出、土砂の不法投棄による損害補償と共に、京浜二区(平和島)三区(昭和島)の埋立計画の中止を港湾局に要求した。これに対し都港湾局は、当面の土砂投棄を禁止し、さらに浚渫業者連名の陳謝状を提示し誠意をもって対応することを約し、今後の投棄作業の誘導監視、不法業者の処罰などを確約した。補償協定は昭和35年に都漁連傘下の16漁協との間で締結され、34年の土砂投棄による損害に対して総額1644万円が支払われた。
東京港の復興と拡張は昭和23年豊洲石炭埠頭の建設に始まり、昭和27年には外国貿易港としての品川埠頭に着工する。巨大な大井埠頭の建設が計画され、浚渫(しゅんせつ)土砂は大井埠頭の埋立て予定地に投棄されていた。都港湾局はこれらの港湾施設だけでなく、昭和30年代に入ると、戦前に中止したままになっていた勝島から森が崎沖までの、京浜二区三区の埋立て工事再開に踏み切る。
大井埠頭埋立て工事の象徴は、予定海域の南側を仕切る長さ約700メートルの石枠護岸で、土砂の投棄による汚水の流出防止が理由とされたが、やがては大井埠頭の外郭堤防の一環とすることが意図されていた。大森漁協ではこの突堤の存在によって、大正場一帯の潮の流れが悪くなり、海苔漁場が荒廃することを恐れその築造に抗議した。一方森が崎沖までの埋立て工事再開の象徴は、平和島の埋立て予定地のうち既に埋立てが完了していた一画に、新たに建設されることになった工事用の受電所であった。京浜二区の埋立て工事再開により、さまざまな漁場への悪影響が予測されたため、漁協はこの受電所の建設に反対した。
昭和34年5月〜6月にかけて大森漁協と港湾局の間で交渉がもたれ、漁協は石枠護岸の撤去を求め、受電所建設に抗議し、大正場の被害に対する補償を要求した。港湾局は2月以降の工事分を旧に復し補償に応じることや、今後の海面に関わる工事は漁民の了解無しには着工しないことなどを確約したものの、(突堤の中間に100メートルの潮どおしをつくることを提案するなどして、)既設の石枠護岸や受電所の撤去要求そのものには応じなかった。(港湾局としては、全体の工事計画そのものが御破算になりかねないような要求は到底受け入れられなかったのであろう。)
この段階に至って、港湾施設の建設と内湾漁業の継続は完全に矛盾し、双方の利害の対立が決定的となる様相を呈してきた。都は抜本的な解決に向け、港湾局を窓口とした対応ではなく、都庁全体としてこの問題に取組むべく、昭和34年8月に東京都内湾漁業対策審議会を設置した。
審議会は漁業権の放棄を前提として、補償対策に取組んでいくことになる。京浜運河構想に基づく埋立てに関しては、戦前に既に補償が支払われていた経緯もあったが、既補償額を差引くことに対する反対を勘案し、差引きを強行する姿勢を避ける一方、全ての埋立て工事が一気に行われるわけではないとの理由で、工事を当面実行する陸側と、5年後から行うその沖側の二期に分け、羽田空港から葛西にかけての湾岸沿いに「Aライン」と称する線引きを行って、補償を「Aライン」の内外で2段階に区分する方式を打出し、Aライン外側の漁場価値低下、損失度合などを把握するために、毎年漁業の実態調査を行うことなどを内容とする対策案を明示した。
漁業権放棄に関わる補償交渉に先立って、昭和35年5月から大井埠頭の埋立てにより発生した被害についての補償交渉が行われたが、大森漁協は埋立てそのものに反対する姿勢に終始し、依然として突堤の撤去を要求、漁業実態調査は拒否するという強行姿勢をとり続けた。
昭和36年2月になると、中部7漁協(品川浦・品川東部・芝・金芝・中央隅田・佃島)からも、大井埠頭埋立てによる被害を受けているとして、都に交渉の開始を要請してきた。その一方3月には城東・深川浦の両漁協から全面補償の早期解決を求める要望が都や都議会に出された。このように都漁連傘下の17漁協の態度は一本化されておらず、交渉は複雑な様相を呈していくことになる。
大井埠頭埋立て問題は、昭和36年5月大森漁協に対して2億6460万円、6月中部7漁協に対して7924万5000円の補償額で交渉が妥結し契約調印となった。
大井埠頭問題の解決を受けて、漁業権放棄に関わる全面補償交渉が始まる。漁協側は都漁連の内湾漁業対策委員会が交渉にあたることになった。委員は総数48名でその内大田区の漁協の割合は、大森6、糀谷浦3、羽田浦4、都南羽田3、第三羽田2(打瀬網業者)の18名だった。
昭和36年9月に第一回内湾漁業対策協議会が開かれ、都により補償対策の方針が説明された。Aラインの内側区域は全面の永久補償とし、協定成立と同時に漁業権を放棄する。Aラインの外側区域は漁業価値低下にともなう生産減の割合に応じた損失について永久補償し、将来の最終補償に於いては既補償額を差引くとした。
Aラインの是非について議論が交わされたが、Aライン内の漁業権が放棄され工事が行われれば、Aラインの外側漁場も荒廃することは明らかであり、漁協側からは、Aラインを撤廃し全面補償すべきという意見が強く出された。これに対して東京都側は、Aラインの移動や拡張試案を出したが受入れられず、協議会はAラインの存廃を巡って膠着状態に陥った。
漁場の状態がどのように変わっていくかの予測はつかず、当分漁業を続けるか転業するかについて組合員個々の判断は難しいものがあったはずである。各漁協に於いてAラインのウエートは異なり、しかも所属の組合員をAラインの内外に明確に区分することは不可能であるなど、Aラインの設定は各漁協の内部に複雑な問題を投げかけ、漁協はその対応に苦慮する結果となっていた。
羽田浦・都南羽田両漁協の漁場は大半がAラインの外側にあった。昭和36年(1961)10月550人の組合員が、Aライン撤廃と全面補償を要求する陳情を都知事と都議会議長に行ったのち、内湾漁業対策協議会から離脱した。同年11月、東京都はAラインの撤廃を決意し、後期5ヵ年の工事を繰り上げ実施し、全漁業権を一括して放棄させ、その補償を行う方針を決定した。これにより両漁協も交渉の場に復帰した。
昭和37年は2年後に迫ったオリンピック東京大会の開催を控えて、京浜二区・三区の埋立てと首都高速道路建設の早期着工が強く望まれていた。3月東京都側は、内湾漁業対策協議会下部機構の促進協議会に於いて、総額270億円の補償金額を提示し、4月には本協議会を開催した。補償交渉は困難を極めたが都議会議長の斡旋により8月に決着した。
提示額を不満とした葛西浦漁協により港湾作業妨害事件が起こされるなど、その後も各漁協への配分額の決定、組合員個々に対する配分をめぐって紛糾があったが、大森漁協では12月1日臨時総会を開いて、漁業権放棄・補償額承認・配分委員会設置などの案件を決議し、他の漁協でも相前後して総会を開催、同様の決議を行った。
かくして漁業従事者による35年間の闘争は終結し、東京湾内湾漁業は完全に終焉することになったが、漁業権放棄後も羽田でアナゴ漁、貝類採取を細々と続けている人たちが居るそうである。
下に現在の臨海部の埋立状況図を示した。(画像をクリックすると詳細な拡大図が別ウインドウで開く。)
埋立地は神奈川側は主として化学コンビナートや製鉄工場などで占められる臨海工業地帯となっているが、東京側では港湾施設のほか、羽田寄りに流通センターや小規模工場の集積地があり、都心側にはウオーターフロント的な開発や各種の公園類・レジャー施設・展示場など様々な用途がみられる。
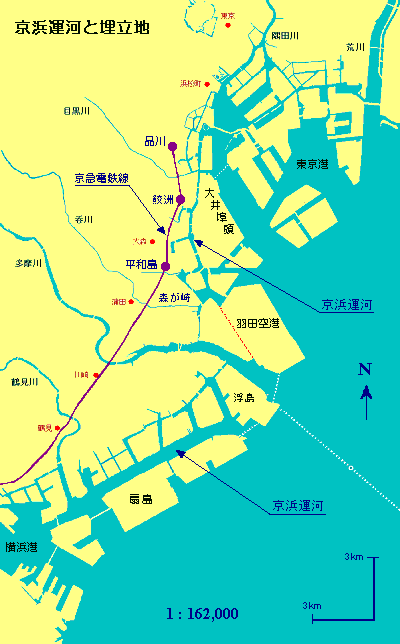 図に京急電鉄線(戦前は京浜電気鉄道)のラインを記入したのは、昭和初期頃の海岸線の位置を推測するためである。京急電鉄線は川崎から東京に入ると、旧東海道(第一京浜国道)に沿って敷設されていたので、平和島から品川までは海岸線に近いところを走っていたことになる。平和島が造られる前の駅名は「学校裏」で、駅は海辺になる「大森町」の中心街の西寄りにあった。「学校裏」を出てから品川町の直ぐ手前になる「鮫洲」(さめず)までの間は、ほぼ海岸線伝いに進み、実際大井町に入る辺りには「海岸」という駅名があって、駅の前は東海道越しに海水浴場が広がっていた。
図に京急電鉄線(戦前は京浜電気鉄道)のラインを記入したのは、昭和初期頃の海岸線の位置を推測するためである。京急電鉄線は川崎から東京に入ると、旧東海道(第一京浜国道)に沿って敷設されていたので、平和島から品川までは海岸線に近いところを走っていたことになる。平和島が造られる前の駅名は「学校裏」で、駅は海辺になる「大森町」の中心街の西寄りにあった。「学校裏」を出てから品川町の直ぐ手前になる「鮫洲」(さめず)までの間は、ほぼ海岸線伝いに進み、実際大井町に入る辺りには「海岸」という駅名があって、駅の前は東海道越しに海水浴場が広がっていた。
鮫洲の先は海岸沿いに南品川宿や猟師町があり、京急はやや海岸線から離れるが、目黒川の河口(今の河口位置はその後天王洲アイルの所で南側に修正されている)で再び海岸に寄り、品川駅も西側に八つ山という小さな埋立地があったものの、海岸線にかなり近い位置にあった。
京浜運河計画が決まった当時のこの界隈の海岸線は、羽田では海老取川から森が崎を経て大森町(学校裏)に向かう線で、大森町から北側は、京急ラインの高々数百メートル東側にあって、一帯は羽田洲から連なる遠浅の浜になっていたのである。
現状図を一目見て分かるように今では、羽田から品川に至る間に海浜ないし沿岸漁業の余地は全く無い。戦争を挟んで埋立地の用途が変わるなど紆余曲折はあったが、品川から羽田に至る現在のこの姿は、昭和2年の内務省港湾調査会による埋立計画図と大勢に於いて変わるものではない。
首都という立地条件で開発と漁業が調和できるはずはなく、双方は開発を進めれば漁業が消滅するという表裏の関係にある。ただ全域の開発が完工するには長い年月を要し、ただちに全ての漁場が物理的に失われるというわけではない。
その一方近年の諫早湾干拓で示されたように、周辺に於ける人為的な環境改造が、自然環境を保全してこそ成り立つ漁業に与える影響には計り知れないものがある。
戦後の東京湾内湾漁業の存亡史は、都港湾局が、存続する漁業(抵抗する漁民)にどこまで配慮し補償しながら開発を進めていったのかという過程を示すと同時に、当時唯一の自然環境保護勢力であったともいえる漁業(従事者)が、どのようにして高度経済成長政策に押し潰されていったのかという過程を示すものともいえるだろう。
図面に関連して若干補足すると、現在多摩川河口の北(東京側)と南(神奈川側)の臨海埋立地それぞれに、京浜運河と称する運河があるが、双方は規模の点で大きく異なるものである。
神奈川県側の京浜運河は昭和2年の「京浜運河構想」の内容に近い(あるいは計画を超える)ものを実現している。計画では運河はその規模で東京港に延長されることになっていたが、東京側の開削が進まないまま敗戦になり、東京側では計画そのものがが廃止されてしまった。
その後の昭和30年代、東京都の側ではもはや運河のことは眼中に無く、航空機のジェット化に備えるべく、羽田空港の一大拡張整備計画を実施していた。同じ時期神奈川県の側では、空港拡張で行く手を阻まれた格好になった京浜運河を「川崎港」として完結させるべく、多摩川右岸の延長線を遥か沖合まで埋立て(浮島)、京浜運河を突き当てる形で終点とさせ、そこに川崎港の港口を作った。
昭和30年代に東京オリンピックを目標に行われた空港の拡張整備で、多摩川の左岸が見掛け上延長した部分は、上掲した詳細図の空港敷地内に赤鎖線で仕切った内側までである。(因みに図にある現状の敷地は昭和59年に着工され、現在最終段階に入っているオキテンによってその後に拡張されたものである。) この間神奈川県側では、京浜運河の外側に扇島、東扇島などを埋立てる方向に進んだ。
現在東京港に入るコンテナ船は大井埠頭を目標に、中央防波堤と城南島の間(東京港第一航路と呼ばれる)を航行している。昭和2年の京浜運河構想に於ける汽船運河は、現川崎側の運河をその規模で延長し、多摩川河口沖を回って現在の大井埠頭の方向に入っていくようになっており、東京側のメイン運河の位置は、現在の空港敷地のど真ん中を通っていたとみなされる。
今東京側で京浜運河と呼ばれているのは、品川埠頭の裏側から始まり、大井埠頭の陸側を通って京浜島と昭和島の間に出、羽田空港の北西側に抜けるまでを言う。戦前に埋立が始まった区域と、戦後新たに埋立を開始した大井埠頭との境目を仕切る幅100メートル程度の運河で、昭和2年当初の計画において汽船運河の内側埋立地に作るとしていた艀(はしけ)用の航路にも満たない小規模の運河である。
(以下東京都のHP「東京ベイエリア21」の策定にあたってより引用)
国際貿易における貨物輸送の大部分は船舶による海上輸送に頼っており、なかでも、1960年代以降は、国際規格に基づくコンテナに対応した大型船により、基幹航路間を定期的に結ぶコンテナ物流が主流となっている。
東京港は、昭和42(1967)年に品川ふ頭にわが国初の国際コンテナターミナルを稼動させ、その後、大井ふ頭や青海ふ頭にも外貿コンテナ機能の拡充を進めてきた。この結果、平成11(1999)年における外貿コンテナ貨物取扱高は、約3,338万トンであり、全国一の取扱高となっている。
また、首都圏の中央部に位置する立地の優位性から、東京港を経由する輸入コンテナ貨物は、その取扱高を拡大し続け、首都圏におけるシェアは、横浜港を有する神奈川県を除く5県ではいずれも、5割を超えるシェアを有している。
2003年1月東京都は中央防波堤内側埋立地の東半分(詳細図で薄緑に塗った部分)を、次世代に引継ぐ大きな森林公園にする方針を決定したと報道された。100年を超えるような長い期間をかけて森を育てるのだという。(2003.1.9 東京新聞夕刊) かつて羽田も大師河原も、その浜は白砂に松が映える景勝の地だった。時代は移り舞台は回る...ということか。
 [参考集・目次]
[参考集・目次]
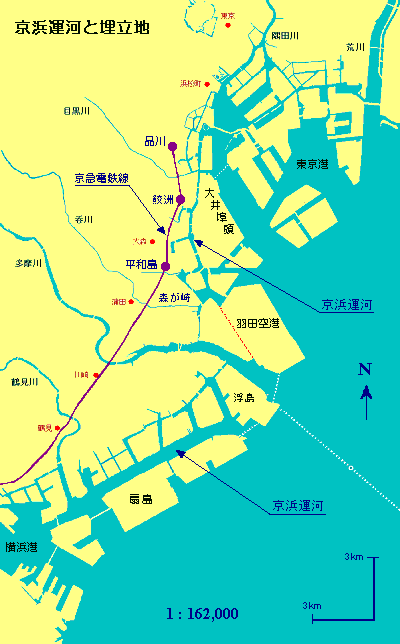 図に京急電鉄線(戦前は京浜電気鉄道)のラインを記入したのは、昭和初期頃の海岸線の位置を推測するためである。京急電鉄線は川崎から東京に入ると、旧東海道(第一京浜国道)に沿って敷設されていたので、平和島から品川までは海岸線に近いところを走っていたことになる。平和島が造られる前の駅名は「学校裏」で、駅は海辺になる「大森町」の中心街の西寄りにあった。「学校裏」を出てから品川町の直ぐ手前になる「鮫洲」(さめず)までの間は、ほぼ海岸線伝いに進み、実際大井町に入る辺りには「海岸」という駅名があって、駅の前は東海道越しに海水浴場が広がっていた。
図に京急電鉄線(戦前は京浜電気鉄道)のラインを記入したのは、昭和初期頃の海岸線の位置を推測するためである。京急電鉄線は川崎から東京に入ると、旧東海道(第一京浜国道)に沿って敷設されていたので、平和島から品川までは海岸線に近いところを走っていたことになる。平和島が造られる前の駅名は「学校裏」で、駅は海辺になる「大森町」の中心街の西寄りにあった。「学校裏」を出てから品川町の直ぐ手前になる「鮫洲」(さめず)までの間は、ほぼ海岸線伝いに進み、実際大井町に入る辺りには「海岸」という駅名があって、駅の前は東海道越しに海水浴場が広がっていた。